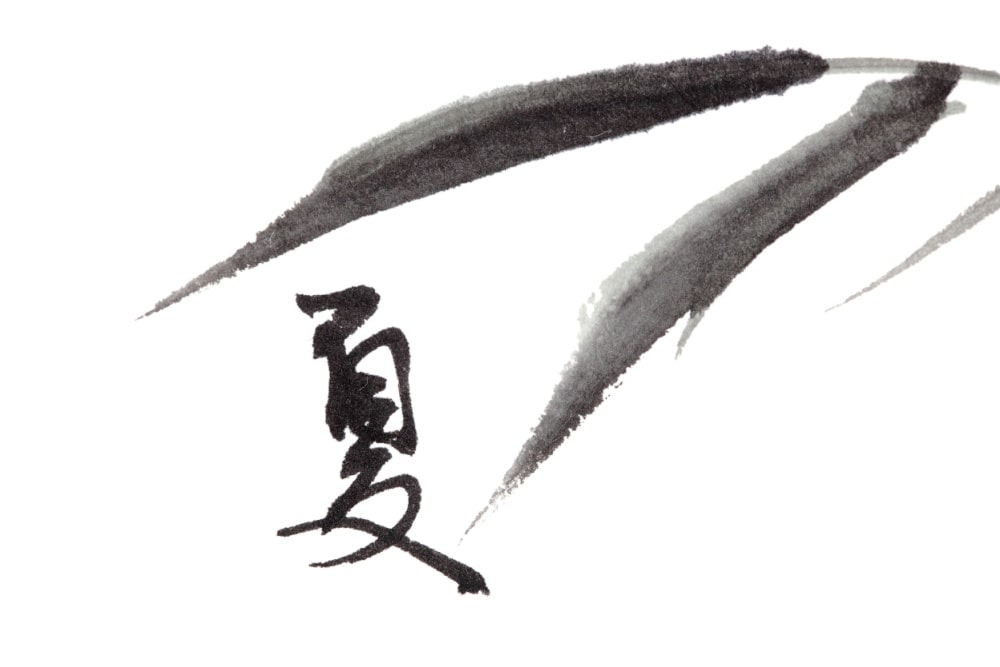「3Dペンで空中に絵を描けるって本当?どうやって作るんだろう……」
そんな疑問を持ちながら、3Dペンアートに興味を持っている方も多いのではないでしょうか。
3Dペンは、溶かしたプラスチックを使って空間に立体的な作品を描ける画期的なツールです。しかし、平面の絵とは違い「どこから作り始めればいいの?」「崩れずに立たせるコツは?」といった疑問もあるはず。
この記事では、3Dペンで立体アートを作るための基本的な仕組みから、必要な道具、具体的な制作ステップ、そして初心者でも作れる作品アイデアまでを詳しくお伝えしていきます。
さらに、子どもと一緒に楽しむための安全対策や、作品をもっと魅力的にする応用テクニックもご紹介していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
3Dペンで「立体表現」は本当にできる?仕組みと基本原理をやさしく解説
まずは3Dペンがどうやって立体作品を生み出すのか、その基本的な仕組みからお話ししていきます。
「本当に空中に描けるの?」という疑問は、多くの初心者が最初に抱くもの。ここでは、3Dペンの構造と立体化の原理を分かりやすくご紹介していきますので、安心して読み進めてみてください。
3Dペンとは?仕組みと立体を作れる理由
3Dペンとは、熱で溶かしたプラスチック素材を押し出して、空間に立体的な造形を描けるペン型のツールのことです。
通常のペンがインクを紙に定着させるのに対し、3Dペンは「フィラメント」と呼ばれる樹脂を内部で加熱し、ノズルから押し出していきます。押し出された素材は数秒で冷えて固まるため、紙がなくても形を保てるのが最大の特徴。
この冷却による固化プロセスが、立体造形を可能にしているというわけです。
家庭用3Dプリンターと似た原理ですが、3Dペンは手で自由に動かせるため、直感的に造形を楽しめます。複雑なソフトウェアも不要なので、初心者でも気軽にチャレンジできるのが魅力ですね。
なぜ「空中に描ける」のか?立体化のカギは冷却スピード
では、なぜ3Dペンは空中に線を描けるのでしょうか。
その秘密は、フィラメントの「急速な冷却」にあります。ノズルから出た瞬間は約200℃前後のドロドロした状態ですが、空気に触れることで一気に温度が下がり、数秒で固体化するのです。
特にPLA(ポリ乳酸)という素材は、冷却スピードが速く、常温でもしっかり硬化します。そのため、垂直方向にペンを動かしても形が保たれ、空中に線を引くことができるというわけです。
ただし、冷える前に手を離したり、急に角度を変えたりすると崩れてしまうことも。
慣れないうちは、少しずつペンを動かして固まるまで待つことがポイントになります。この「待つ感覚」をつかめれば、立体表現の幅が一気に広がっていきますよ!
平面と立体の違いとは?初心者がつまずきやすいポイント
紙に絵を描くときと、3Dペンで立体を作るときでは、考え方が根本的に異なります。
平面の場合、線を引けばそのまま紙に定着しますが、立体では「どの方向に、どのくらいの長さで線を引くか」を常に意識しなければなりません。なぜなら、空間には支えがないため、設計なしに描くとすぐに崩れてしまうからです。
また、立体物は「前後・左右・上下」の三次元で構成されるため、頭の中で完成形をイメージする力も求められます。
初心者がつまずきやすいのは、まさにこの「三次元での設計思考」の部分。
しかし、最初はシンプルな形(四角や三角)から始めれば大丈夫です。慣れてくると、複雑な形でもパーツに分解して組み立てる感覚が身につきますので、焦らず一歩ずつ進んでいきましょう!
初心者でも安心!立体アート制作に必要な道具とおすすめ3Dペン
ここからは、3Dペンで立体アートを作るために必要な道具と、おすすめの3Dペンをご紹介していきます。
「何から買えばいいのか分からない……」という方も多いはず。
そこで、初期費用を抑えながらも快適に制作できる道具選びのポイントをお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!
まず揃えたい基本道具一覧(3Dペン/フィラメント/作業マットなど)
3Dペンを使った立体アート制作には、最低限以下の道具が必要です。
【必須アイテム】
- 3Dペン本体
- フィラメント(樹脂素材)
- 作業マット(シリコンマットや耐熱シート)
- トレーシングペーパー(下絵を写すため)
【あると便利なアイテム】
- カッター・ニッパー(余分な部分のカット用)
- ピンセット(細かいパーツの固定用)
- 定規・コンパス(正確な形を作るため)
- 型紙や設計図
初期費用の目安としては、3Dペン本体が3,000円〜10,000円程度、フィラメントが1,000円〜2,000円で、合計5,000円前後から始められます。
作業マットは100円ショップのシリコン製でも十分ですし、トレーシングペーパーも文房具店で手軽に入手可能です。
まずは最小限の道具で始めて、慣れてきたら少しずつ追加していくのがおすすめですよ!
初心者におすすめの3Dペン|価格・性能・安全性で選ぶ
次に、初心者でも使いやすい3Dペンを具体的にご紹介していきます。
選ぶ際のポイントは「価格」「操作のしやすさ」「安全性」の3つ。特に、温度調整機能やスピード調整機能があると、素材に合わせた細かい調整ができるため便利です。
【おすすめ3Dペン比較表】
| 製品名 | 価格帯 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 3Doodler Start+ | 約7,000円 | 低温ノズル・子ども向け・安全性◎ | ★★★★★ |
| myFirst 3dpen | 約5,000円 | 軽量・USB充電式・初心者向け | ★★★★☆ |
| MYNT3D Pro | 約8,000円 | 温度調整可能・精密造形向け | ★★★★☆ |
| Polaroid Play | 約4,000円 | コスパ良好・シンプル設計 | ★★★☆☆ |
3Doodler Start+は、低温ノズルを採用しており、触っても火傷しにくい設計になっています。子どもと一緒に使う場合は、安全性を重視したこのタイプが最適です。
一方、より細かい表現を求めるなら、温度調整機能のあるMYNT3D Proがおすすめ。
初めて購入する場合は、まず5,000円前後のエントリーモデルで試してみるのが良いでしょう!
フィラメントの種類と選び方|PLA・ABS・TPUの違いとは?
3Dペンで使うフィラメントには、主に3つの種類があります。
【PLAフィラメント】
- 素材:植物由来のポリ乳酸
- 特徴:低温で溶け、冷却が速い/無臭で扱いやすい
- 向いている用途:初心者の練習・室内での制作
【ABSフィラメント】
- 素材:石油由来のプラスチック
- 特徴:高温が必要・強度が高い/やや臭いがある
- 向いている用途:屋外展示・強度が必要な作品
【TPUフィラメント】
- 素材:ゴムのような弾性素材
- 特徴:柔軟性がある・曲げても折れない
- 向いている用途:アクセサリー・柔らかい質感の作品
初心者には、扱いやすく安全性の高いPLAフィラメントがおすすめです。
なぜなら、溶ける温度が低めで、冷却も速く、失敗しても修正しやすいからです。
フィラメントは1kgあたり1,500円〜2,500円程度で購入でき、色のバリエーションも豊富。
まずは基本の5色セット(赤・青・黄・緑・白)を揃えて、カラフルな作品作りを楽しんでみてください!
立体作品づくりの基本ステップ5つ|くずれない作り方とコツ
ここからは、3Dペンで立体作品を作る具体的なステップをご紹介していきます。
「どこから作り始めればいいの?」「どうすれば崩れずに立つの?」という疑問を持つ方も多いはず。
しかし、正しい手順を踏めば、初心者でもしっかりとした立体作品を作れますので、一つずつ丁寧に見ていきましょう!
ステップ1|作品を分解して設計しよう(型紙や下絵の使い方)
立体作品を作る第一歩は、完成形を「パーツに分解して考える」ことです。
たとえば、立方体を作りたい場合、いきなり空中で組み立てようとするのは困難。そこで、まず「正方形を6枚作る」→「それを組み合わせる」という発想に切り替えます。
このように、複雑な形でも単純なパーツの組み合わせとして捉えれば、制作のハードルが一気に下がるのです。
型紙や下絵は、イラストや写真をトレーシングペーパーに写すだけでOK。ネット上には無料でダウンロードできる3Dペン用テンプレートもたくさんありますので、活用してみると良いでしょう。
設計段階で「どのパーツから作るか」「どの順番で組み立てるか」を明確にしておくことが、成功への近道になります!
ステップ2|まずは平面でパーツを作る
次に、設計したパーツを実際に平面で作っていきます。
ここでポイントになるのが、トレーシングペーパーの活用です。下絵の上にトレーシングペーパーを置き、その線をなぞるように3Dペンで描いていくと、正確な形のパーツが作れます。
フィラメントが冷えて固まったら、トレーシングペーパーからゆっくり剥がしましょう。
もし線が細すぎて強度が不安な場合は、同じ線を2〜3回重ねて描くと補強になります。また、パーツの端は少し太めに描いておくと、後で組み立てる際に接着しやすくなるのでおすすめです。
平面パーツをしっかり作れるようになると、立体作品の完成度が格段に上がりますよ!
ステップ3|パーツを立体的に組み立てるコツ
平面パーツが揃ったら、いよいよ立体に組み立てていきます。
組み立ての基本は「接着面を3Dペンで溶接する」こと。パーツとパーツが接する部分に、少量のフィラメントを押し出して固定していきます。
垂直に立ち上げる場合は、土台となるパーツをしっかり固定してから、垂直パーツをゆっくり押し当てるのがコツ。このとき、完全に固まるまで手を離さず、数秒間支えておくことが重要です。
また、斜めの角度で接着する場合は、角度を保つための「仮支え」を用意しておくと便利。
たとえば、消しゴムや粘土を使って一時的に固定すれば、両手が自由になり作業がしやすくなります。
組み立ての順番は「土台→側面→上部」が基本ですが、作品によって最適な順序は変わりますので、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします!
ステップ4|強度アップ&補強テクニック
立体作品を作る上で気になるのが「強度」です。
特に、細い線だけで組み立てた作品は、少しの衝撃で壊れてしまうことも。そこで、強度を上げるための補強テクニックをいくつかご紹介していきます。
【補強の基本テクニック】
- 線の重ね塗り:同じ場所を2〜3回なぞって太くする
- フレーム構造:内部に骨組みを作り、外側を覆う
- 接着部分の強化:パーツの接合部に多めのフィラメントを盛る
- 乾燥時間の確保:完全に冷えるまで触らない
また、大きな作品を作る場合は、内部にワイヤーや竹串を仕込む方法も有効です。
このように、芯材を入れることで曲がりにくくなり、形も安定します。
ただし、ワイヤーを使う場合は、先端で怪我をしないよう注意が必要。特に子どもと一緒に作る際は、大人が管理するようにしましょう。
補強テクニックを身につければ、持ち運びできる作品や、飾って長く楽しめる作品が作れるようになりますよ!
ステップ5|表面仕上げで作品の完成度アップ
最後に、作品の表面を整えて仕上げていきます。
3Dペンで作った作品は、どうしても線の凹凸が目立つもの。そこで、表面をなめらかにするための仕上げテクニックが役立ちます。
まず、余分なフィラメントは、カッターやニッパーで丁寧にカットしましょう。特に、接着部分の「はみ出し」は目立ちやすいので、しっかり処理すると見た目が良くなります。
また、凹凸を埋めたい場合は、細い線を何度も重ねて「面」を作る方法も有効です。
さらに、カラフルな作品にしたいなら、異なる色のフィラメントを追加で盛っていくと、立体的な模様や装飾が楽しめます。
他の素材との融合もおすすめ。たとえば、布やビーズ、LEDライトなどを組み合わせれば、オリジナリティあふれる作品に仕上がります。
最後にウェットティッシュで表面を軽く拭けば、手垢や汚れも取れて、よりきれいな見た目になりますよ!
3Dペンアートのおすすめ立体作品5選|初心者でも作れるアイデア集
ここからは、初心者でもチャレンジしやすい立体作品のアイデアを5つご紹介していきます。
「何を作ればいいか分からない……」という方は、まずこれらの作品から始めてみることをおすすめします!
作品①:かわいい動物フィギュア(猫・パンダなど)
動物フィギュアは、3Dペン初心者に最も人気のある作品です。
特に、猫やパンダなどの丸みのある動物は、パーツが少なくシンプルな構造なので作りやすいのが特徴。
【制作の流れ】
- 頭・胴体・手足・耳などのパーツを平面で作成
- 各パーツを組み立てて立体化
- 目や鼻をカラーフィラメントで追加
難易度:★★☆☆☆ 制作時間:30分〜1時間 材料コスト:約300円
ポイントは、耳や尻尾など「突起部分」を最後に付けること。先に付けると組み立て中に折れてしまうことがあるためです。
また、顔のパーツは黒や茶色のフィラメントで細かく描き込むと、表情豊かな仕上がりになります。
まずは簡単なシルエットから始めて、慣れてきたら細部にこだわってみると良いでしょう!
作品②:植物&自然モチーフ(きのこ・ミニ盆栽)
植物モチーフも、初心者におすすめの立体作品です。
特にきのこは、傘の部分と柄の部分を別々に作って組み合わせるだけなので、非常にシンプル。
【制作の流れ】
- 傘の部分を円形に描く
- 柄の部分を円柱状に作る
- 傘を少し曲げて立体感を出し、柄と接着
難易度:★☆☆☆☆ 制作時間:15分〜30分 材料コスト:約200円
さらに、ミニ盆栽風の作品も人気があります。細い枝を何本か作り、小さな葉を付けていけば、インテリアとしても楽しめる作品が完成します。
緑・茶色・白などのフィラメントを使い分けることで、自然な色合いが表現できるのもポイント。
植物モチーフは失敗しても「味」になりやすいので、気軽にチャレンジしてみてください!
作品③:小物雑貨(ペン立て・スマホスタンド)
実用性のある小物雑貨も、3Dペンで簡単に作れます。
ペン立ては、円柱状の枠を作るだけなので、初心者でも失敗が少ない作品です。
【制作の流れ】
- 底面となる円を描く
- 側面の壁を垂直に立ち上げる
- 高さ5〜10cmで完成
難易度:★★☆☆☆ 制作時間:30分〜45分 材料コスト:約400円
スマホスタンドは、L字型の構造を作るだけでOK。背面に支えとなる「足」を付ければ、しっかり自立します。
また、ペン立てやスマホスタンドは、表面に模様を描き込んだり、カラフルな装飾を加えたりすることで、オリジナリティが出せるのも魅力です。
日常的に使える作品を作れば、達成感も倍増しますよ!
作品④:アクセサリー(イヤリング・バッジ)
3Dペンは、小さなアクセサリー作りにも最適です。
特にイヤリングやバッジは、平面パーツを少し立体的にするだけで作れるため、短時間で完成します。
【制作の流れ】
- 好きな形(星・ハート・花など)を平面で描く
- 少しだけ立体感を出すために、中央を盛り上げる
- 金具を取り付けて完成
難易度:★☆☆☆☆ 制作時間:10分〜20分 材料コスト:約100円(金具別)
イヤリングの場合、手芸店で購入できる「イヤリング金具」を3Dペン作品に接着剤で付けるだけ。バッジなら、裏面に安全ピンを固定すれば、すぐに身につけられます。
カラフルなフィラメントを使えば、ポップでかわいいアクセサリーが作れますし、透明フィラメントを使えば、涼しげで大人っぽい雰囲気にも仕上がります。
自分用に作るのはもちろん、プレゼントとしても喜ばれますよ!
作品⑤:自由研究や展示にも!ユニークな立体模型
最後にご紹介するのは、学校の自由研究や展示にも活用できる立体模型です。
たとえば、恐竜の骨格模型や、建築物のミニチュア、分子構造モデルなど、教育的な要素を含んだ作品は、学びながら楽しめるのが魅力。
【制作の流れ】
- 資料を参考に設計図を作成
- パーツを細かく分けて制作
- 組み立てながら構造を理解
難易度:★★★☆☆ 制作時間:1時間〜3時間 材料コスト:約500円〜1,000円
このタイプの作品は、制作過程そのものが学習になるため、子どもの自由研究にぴったりです。また、完成後は展示物として長く飾っておけるのも嬉しいポイント。
理科や社会、美術など、さまざまな教科と結びつけられるので、興味のあるテーマを選んで挑戦してみてください!
子どもと一緒でも安心!安全に楽しく使うための注意点と工夫
3Dペンは、子どもでも扱える道具ですが、熱を使う以上、安全対策は欠かせません。
ここでは、保護者や教育者の方に向けて、安全に楽しむための注意点と工夫をお伝えしていきます。
3Dペンの安全性は?高温ノズルに注意
3Dペンで最も気をつけるべきは、ノズル部分の高温です。
フィラメントを溶かすため、ノズルは約180℃〜230℃まで熱くなります。誤って触れると火傷の恐れがあるため、使用中は絶対にノズルに触らないよう注意しましょう。
また、作業中は以下のポイントにも気を配ってください。
【安全対策のポイント】
- 作業前に「触ってはいけない場所」を明確に伝える
- 使用後はペンスタンドに立てて冷ます
- 長時間連続で使用せず、適度に休憩を入れる
- 換気をしながら作業する(フィラメントが溶ける際の微量な煙対策)
さらに、万が一のために、作業場所の近くに冷たい水を用意しておくと安心です。
火傷をした場合は、すぐに冷水で冷やし、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
安全対策をしっかり行えば、子どもでも楽しく安全に3Dペンアートを楽しめますよ!
子どもにおすすめの3Dペンとフィラメント選び
子どもが使う場合は、「低温ノズルタイプ」の3Dペンを選ぶことが重要です。
低温ノズルタイプは、通常の3Dペンよりも低い温度(約100℃前後)で動作するため、万が一触れても重度の火傷になりにくいのが特徴。
【子ども向け3Dペンの選び方】
- 低温ノズル仕様であること
- 軽量で握りやすいデザイン
- 自動オフ機能付き(一定時間操作がないと自動で電源OFF)
- 無臭または低臭のフィラメント対応
フィラメントに関しては、PLAフィラメントが最も安全。植物由来の素材なので、溶ける際の臭いもほとんどなく、換気が十分でない室内でも使いやすいのが魅力です。
また、カラフルな色が揃っているため、子どもの創作意欲を刺激してくれます。
安全性と楽しさの両立を考えるなら、これらのポイントを押さえた製品を選んでみてください!
安全に楽しむための工夫と親子での使い方アイデア
親子で3Dペンを楽しむ場合、一緒に作業することで安全性が高まります。
たとえば、大人が熱いノズル部分を扱い、子どもは冷えたパーツの組み立てを担当するなど、役割分担をするのも良い方法です。
【親子で楽しむための工夫】
- 作業スペースを広く確保し、机に耐熱マットを敷く
- 作業前に「安全ルール」を一緒に確認する
- 完成した作品を写真に残して、成長の記録にする
- 定期的に休憩を取り、集中力が切れないようにする
また、使い終わったあとの片付けまでを「制作の一部」として習慣づけることも大切です。フィラメントの残りを整理したり、ペンをきれいに拭いたりすることで、道具を大切に扱う心も育まれます。
安全対策をしっかり行いながら、親子で楽しい時間を過ごしてみてください!
【さらに知りたい人へ】立体アートをもっと楽しむ!応用テクニック&発展アイデア集
ここからは、3Dペンに慣れてきた方向けに、さらに作品の幅を広げる応用テクニックをご紹介していきます。
「もっと挑戦したい!」と感じた方は、ぜひ読み進めてみてください!
ワイヤーやLEDと組み合わせた立体造形
3Dペンとワイヤーを組み合わせると、より複雑で自由度の高い作品が作れます。
たとえば、針金で骨組みを作り、その上から3Dペンでフィラメントを巻きつけていけば、大型の作品でもしっかりした構造が作れるのです。
さらに、LEDライトを組み込めば、光る立体アートが完成します。
【LED組み込みのアイデア】
- 花や星のモチーフにLEDを仕込んで光らせる
- ランプシェードを作り、内部にLED電球を配置
- 透明フィラメントを使って、光が透ける作品に仕上げる
また、モーターや電池を使った動く作品にも挑戦できます。たとえば、車のボディを3Dペンで作り、既製のモーターキットと組み合わせれば、走る車が完成します。
このように、他の素材や電子部品と組み合わせることで、作品の可能性は無限に広がっていきますよ!
プロの3Dペン作家の作品を見て刺激を受けよう
上達のコツは、プロの作品を見ることです。
YouTubeやInstagramには、世界中の3Dペンアーティストが作品を公開しています。たとえば、人気YouTubeチャンネル「Sanago」では、驚くほど精密な立体アートの制作過程が紹介されており、見ているだけでも楽しめます。
また、海外のアーティストによる大規模なインスタレーション作品や、ファッションと融合したウェアラブルアートなども注目されています。
【参考になる情報源】
- YouTube:制作過程の動画でテクニックを学ぶ
- Instagram:完成作品の写真でアイデアを得る
- Pinterest:型紙やテンプレートを探す
プロの作品を見ることで、「こんな表現もできるんだ!」という発見があり、自分の作品づくりにも新しいアイデアが生まれます。
まずは好きなアーティストを見つけて、フォローしてみることをおすすめします!
立体表現をもっと楽しむ!SNS映えする作品撮影のコツ
せっかく作った作品は、きれいに撮影してSNSでシェアしてみませんか。
撮影のコツを押さえれば、作品の魅力が何倍にも引き立ちます。
【撮影のポイント】
- 自然光を使う:窓際で撮影すると、影が柔らかく美しい
- 背景をシンプルにする:白い紙や布を敷いて、作品を際立たせる
- 俯瞰アングル:真上から撮ると、全体像が分かりやすい
- 接写で細部を見せる:細かい装飾や質感をアップで撮影
また、複数の作品を並べて撮影する「フラットレイ」スタイルも人気です。カラフルな作品を並べれば、見た目にも楽しい写真に仕上がります。
さらに、制作過程を動画で撮影して、タイムラプス風に編集すれば、より多くの人に興味を持ってもらえるでしょう。
作品を作るだけでなく、撮影や発信まで楽しむことで、3Dペンアートの世界がさらに広がっていきますよ!
まとめ
3Dペンは、溶かしたフィラメントを使って空間に立体作品を描ける、創造性豊かなツールです。
基本的な仕組みを理解し、正しい手順で制作すれば、初心者でも驚くほどクオリティの高い作品が作れます。
必要な道具は3Dペン本体とフィラメント、作業マットなど最小限でOK。価格も5,000円前後から始められるため、気軽にチャレンジできるのが魅力です。
制作のコツは、作品をパーツに分解して考えること、そして平面から立体へと段階的に組み立てていくことです。補強テクニックや表面仕上げを丁寧に行えば、長く飾れる作品が完成します。
また、子どもと一緒に楽しむ場合は、低温ノズルタイプの3Dペンを選び、安全対策をしっかり行うことが大切です。
まずは簡単な作品から始めて、少しずつレベルアップしていきましょう。慣れてきたら、ワイヤーやLEDとの組み合わせなど、応用テクニックにも挑戦してみてください。
3Dペンアートは、アイデア次第で無限の可能性が広がる世界です。
あなたもぜひ、手のひらサイズの小さな作品から、大きな夢のある立体アートまで、自由に創作を楽しんでみてください!